小学校に上がると、必ず覚えなければいけないのが慣用句です。国語のテストでは、必ずといっていいほど穴埋め形式で出題されますね。また慣用句を理解していないと、長文の読解でつまづいてしまいます。だから慣用句を覚えなければいけないといっても、学校の宿題や習い事で忙しく、ゆっくり勉強する暇もなかなか取れませんね。そこで今回は私と小学生の娘が実践している、慣用句の効率的な覚え方についてまとめたいと思います。
慣用句とは?
慣用句とは、日常的な出来事を何かに例えて表現している言葉です。ことわざとは違い、教訓や格言などは含んでいません。
「耳が痛い」「骨を折る」「開いた口がふさがらない」など、人の体の一部を使った表現が多いですね。最近ですと、うちの娘には「肩を持つ」という表現が目新しかったようで、日常会話で使用しています。今までは上手く言葉にできなかった気持ちが、慣用句を覚えたことで表現しやすくなったのだと思います。
このように、テスト対策だけではなく、表現力を上げるためにも重要なのだと実感しています。
小2の理沙はSAPIXの通信講座ピグマキッズをとっていますが、
中学受験を意識しているのか慣用句の問題が多いです。
効率的な覚え方
ボイスレコーダー
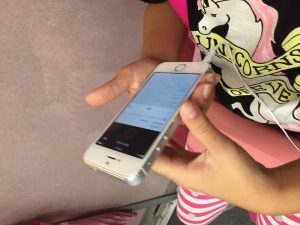
紙に書いて覚えるのは書く時間がもったいないのですし、筆記用具を持ち歩くのもかさばって面倒ですね。そのため、うちではスマホのボイスレコーダーを使用しています。慣用句、意味の順で吹き込みます。スマホでしたら場所や時間を選ばないため、重宝しています。
聞いている時間は主に移動の電車の中や就寝前。イヤホンを使用すれば、電車の中であっても迷惑にはなりづらいです。また寝る前にベッドに入りながらだとリラックスして聞けるようでいいと思っています。
この方法を使うとだいたい3回くらいで覚え、4回目くらいにはしっかりと身についているようです。私も最近は忙しく、オーディオブックを利用し、「ながら読書」を行っていますが、五感(聴覚)を使うと覚えやすい気がします。
ちなみに、スマホを使用すればアプリで慣用句を勉強することもできます。隙間時間で効率良く勉強するためには、スマホの使用は有効的だと思います。
日常で使う
何事もそうですが、実践で使うのが一番効率よく覚えられる方法かもしれません。娘が「肩を持つ」という表現を覚えて使うようになったと書きましたが、これも実践での経験によるもの。
ただそらんじるよりも、具体的な行動と合わせて使うとイメージを掴みやすいようです。例えば、娘がテストで100点を取ったとして、「(母親として)鼻が高い」と言う慣用句を使用すれば、意味と合わせて実践的な使い方もできます。
ただ大人だからといって、すぐさま適切な慣用句を思い出せるわけでもありません。そのため、日常でよく起る出来事に関しては、あらかじめ適切な慣用句がないかを見繕っておく、といった準備をしておくのもいいかもしれませんね。
なお、日常的に使いやすい慣用句として、
・足の踏み場がない(部屋を散らかしたままで、片付けていなかったとき)
・腕が鳴る(得意料理を晩御飯に出すとき)
・間一髪(あやうく事故につながるところに遭遇したとき、乗りたかった電車にぎりぎり間に合ったとき)
・壁に突き当たる(テスト勉強を頑張っているのに、なかなか良い結果が出ないとき)
・肝を冷やす(なにか危ないことに遭遇したが、避けられたとき)
・心を打つ、心を打たれる(感動的な本を読んだり、エピソードを見聞きしたとき)
・舌鼓を打つ(美味しいものと食べているとき)
・力を入れる(勉強やスポーツなどで、特に頑張る分野があるとき)
・手が空く(子供に時間の余裕があり、お手伝いを頼むとき)
・話に花が咲く(面白い話題で盛り上がったとき)
・羽を伸ばす(休日にのんびりできたとき)
・膝を打つ(子供の話に感心したとき)
・虫の居所が悪い(子供の機嫌が良くないとき)
などがあります。
他人をネガティブに形容するような表現は、変に気に入ってしまい、悪口として使ってしまう可能性があります。そういった慣用句の使用は、ほどほどにした方がいいかも?とも思っています。
まとめ
①スマホのボイスレコーダーを使用する
②実践で使う
であれば、お金もかからず、時間を選ぶことなく効率的に勉強できます。使い方を覚えて興味を持ってもらえれば積極的に覚えてもらえるので、自分からどんどん使うようにしています。
現在理沙は小2です。